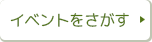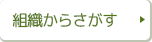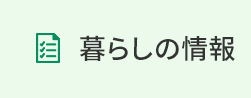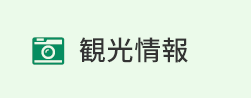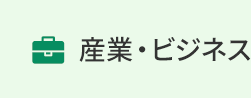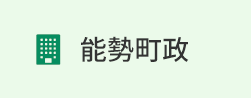調整給付金の支給について
1.定額減税の実施について
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、定額減税が実施されます。
定額減税は、納税者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき4万円がそれぞれ所得税・個人住民税所得割から減税されるものです(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)。今回、所得税や個人住民税が定額減税可能額まで達していない方(定額減税しきれない部分があると見込まれる方)に、調整給付金を給付します。
*調整給付金は、令和6年度個人住民税の課税市町村(令和6年1月1日現在お住まいの市町村)より支給されます。
なお、定額減税については、次をご覧ください。
・所得税の定額減税について
・個人住民税の定額減税について
2.概要
対象となる方(給付要件)
次を満たす方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
・能勢町の令和6年度分個人住民税の納税義務者であること。
・定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された対象者の「令和6年分推計所得税額」(令和5年分所得税額)または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回ること。
※令和6年度の個人住民税は、令和5年1月1日~12月31日までの収入に基づき、令和6年6月ごろに令和6年1月1日時点でお住まいの自治体より、納税通知書が送付されます。(勤務先で住民税が給与から差し引き(特別徴収)されている方は、勤務先より「特別徴収税額通知書」が配付されます。)
支給額と算定方法
支給額 = 所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額
・所得税分控除不足額
定額減税可能額(※1) ー 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)= 所得税分控除不足額
(※1) 3万円×(本人+扶養親族の人数)
・個人住民税分控除不足額
定額減税可能額(※2) ー 令和6年度分個人住民税所得割額 = 個人住民税分控除不足額
(※2) 1万円×(本人+扶養親族の人数)
手続き方法等
・調整給付金の支給対象と思われる方へ、7月下旬に確認書をお送りします。お手元に届いた確認書に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。なお、返送に当たっては、必ず次の添付書類を確認書裏面に貼り付けた上で提出してください。
1.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどのいずれか1点のコピー)
2.振込先金融機関口座確認書類(振込先口座の金融機関、支店、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードなどのコピー)
提出期限
確認書等の提出期限は、令和6年10月31日です。支給を希望される方は、提出期限までに確認書の提出をお願いします。
算定上の注意点
・令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)と令和6年度分個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。
・令和6年分所得税額は未確定のため、調整給付金の算出には令和5年分の所得等を基にした推計所得税額により行います。令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定した後、調整給付金に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
・申告等により生じた所得税および住民税所得割額の修正等については、原則として調整給付の金額に反映しませんが、令和7年度に調整給付の不足分の追加支給を行う予定です。
支給額の算定例
(例1)納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(定額減税前)4,000円(A)
令和6年度分個人住民税額(定額減税前)20,900円(B)
所得税分定額減税可能額 30,000円×(本人+扶養親族3人の計4人)=120,000円(C)
個人住民税分定額減税可能額 10,000円×(本人+扶養親族3人の計4人)=40,000円(D)
1.所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額120,000円(C) ー 令和6年分推計所得税額(定額減税前)4,000円(A)=116,000円(E)
2.個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額40,000円(D) ー 令和6年度分個人住民税額(定額減税前)20,900円(B)
=19,100円(F)
支給額(調整給付額) (E)+(F)=135,100円
→ 支給額は1万円単位で切り上げるので調整給付金の支給額は140,000円となります。
(例2)単身世帯(扶養親族なし)の場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(定額減税前)27,000円(A')
令和6年度分個人住民税額(定額減税前)54,700円(B')
所得税分定額減税可能額 30,000円(C')
個人住民税分定額減税可能額 10,000円(D')
1. 所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額30,000円(C') ー 令和6年分推計所得税額(定額減税前)27,000円(A')=3,000円(E')
2. 個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額10,000円(D') ー 令和6年度分個人住民税額(定額減税前)54,700円(B')=ー44,700円(0円)(F')※マイナスの場合0円
支給額(調整給付額) (E')+(F')=3,000円
→ 支給額は1万円単位で切り上げるので調整給付金の支給額は10,000円となります。
差押禁止等について
本給付金は差押えが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
詐欺にご注意ください
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
能勢町から町民の方に、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、迷わず能勢町福祉部福祉課または警察署にご連絡ください。
令和6年度能勢町低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付) 支給事務実施要綱
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部福祉課福祉担当
能勢町栗栖82番地の1(保健福祉センター)
電話:072-731-2150
ファックス:072-731-2151
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年07月01日