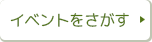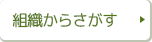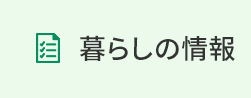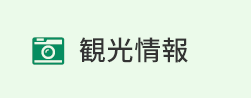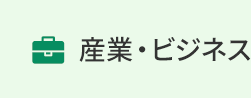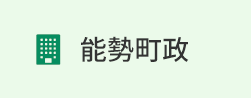後期高齢者医療制度について
制度の運営と各種申請・届出の窓口
後期高齢者医療制度の運営は、大阪府内のすべての市町村が加入する『大阪府後期高齢者医療広域連合』が行います。
申請や届出の受付は、能勢町役場(本庁舎)保険医療担当の窓口で行っています。
後期高齢者医療広域連合と市町村の役割
広域連合(都道府県ごと)が、制度の運営全般を行っています。
〇被保険者の認定・資格管理
〇被保険者証等の交付
〇保険料の決定
〇医療の給付
〇健康診査等の実施 など
能勢町(市町村)が、広域連合と被保険者をつなぐ窓口です。
〇保険料の徴収
〇被保険者証等の引渡・回収
〇各種申請・届出の受付
〇制度に関する各種相談 など
被保険者(対象となる方)
1)75歳以上の方
75歳のお誕生日を迎えられた方は、それまで加入していた健康保険(国民健康保険・社会保険など)から後期高齢者医療制度の被保険者になります。
※生活保護を受給されている方は対象となりません(適用除外)。
2)65歳から74歳の方で、申請により広域連合が一定の障害があると認めた方(障害認定制度)
【対象となる一定の障害】
〇国民年金法等における障害年金1・2級
〇身体障害者手帳1・2・3級および4級の一部
〇精神障害者保健福祉手帳1・2級
〇療育手帳A
◎障害認定後も75歳になるまでの期間は、認定の撤回届により撤回できます。
※障害認定後に対象となる障害に該当しなくなった方は、資格喪失のお手続きと他の医療保険(国民健康保険、社会保険など)の加入手続きが必要となります。
被保険者証と医療機関等での自己負担割合
1)被保険者証
1人1枚の被保険者証を交付します。
※新たに75歳を迎えられる方には、誕生日の前月に被保険者証を書留郵便にてお送りします。
なお、令和6年12月2日以降に75歳を迎えられる方には、「資格確認書」をお送りします。
有効期限は、原則:毎年8月1日から7月31日までです。
※有効期限が切れた被保険者証は使用できません。能勢町役場 保険医療担当能の窓口へ返却いただくか、ご自身での破棄をお願いします。
※令和6年12月2日以降、紙の被保険者証の新規発行ができなくなり、保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みとなります。詳細は、こちらをご覧ください。
※現在、お持ちの被保険者証は、有効期限:令和7年7月31日までお使いいただけます。
2)医療機関等の窓口での自己負担割合
一般所得者:1割
一定以上所得者:2割
◎一定以上所得:現役並み所得者3割判定の方を除く、住民税が課税される所得額(各種所得控除後の所得額)が28万円以上あり、同じ世帯の被保険者の「年金収入とその他合計所得額」の合計が、同じ世帯に
・被保険者:1人の場合、200万円以上
・被保険者が2人以上のいる場合:320万円以上
の被保険者および、この方と同じ世帯に属する被保険者
現役並み所得者:3割
◎現役並み所得者3割判定の方:住民税が課税される所得額(各種所得控除後の所得額)が145万円以上ある被保険者および、この方と同じ世帯に属する被保険者
保険料
1)保険料について
被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。
保険料を決める基準(保険料率)は、各都道府県の広域連合が2年ごとに条例により設定します。
詳しくは、大阪府後期高齢者広域連合のサイトをご覧ください。
※年度途中に被保険者の資格を取得・喪失した場合には月割りで計算します。
2)保険料の納め方
普通徴収:納付書や金融機関からの口座振替にて納付
1年間の保険料を7月から翌年3月までの9か月間に分けて納付いただきます。
※随時期の保険料:3月に75歳になられる方や能勢町へ転入される方には、加入月からの保険料を4月から6月の間に納付をお願いすることがあります。
特別徴収:受給されている年金から保険料を納付
年金受給月(偶数月)に保険料を天引きいたします。
※特別徴収に切り替わる方には、事前に納付通知書等にてご案内をいたします。
「財政運営」社会全体で制度を支えています。
加入者一人ひとりの保険料と現役世代の保険料(75歳未満の方々)、公費(国、都道府県、市町村)によって、窓口負担を除く医療にかかる費用を負担することで、75歳以上の方の医療を国民みんなで支えています。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部住民課保険医療担当(本館1階)
電話:072-731-3202
ファックス:072-734-1100
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年11月05日