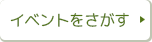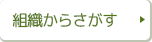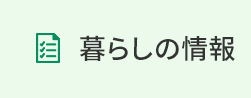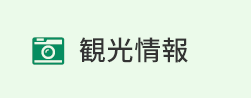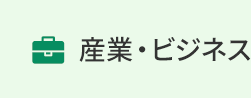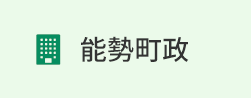(令和7年7月1日更新)市街化調整区域の幹線道路沿道等における工場等の立地を目的とした開発許可基準
(令和7年7月1日更新)審査基準の策定
令和4年4月1日に都市計画法が改正され、原則として災害リスクの高いエリアを開発区域に含むことができなくなったことから、「都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」第5における土砂災害警戒区域(イエローゾーン)及び浸水想定区域での開発行為等に関する取扱いを新たに策定しました。
【概要】
・次のいずれかに該当するものに関しては、開発区域又は建築敷地とすることができる
(土砂災害警戒区域の場合)
(1)土砂災害が発生した場合に、土砂災害防止法第8条第1項に基づき能勢町地域防災計画に定められた同項第2号の避難場所への確実な避難にあたり、開発行為及び建築行為をしようとする者、建築物の所有者、占有者又は管理者等により作成された避難確保計画の能勢町長への報告、同計画に基づいた避難誘導等の訓練の実施、かつ訓練結果報告を受けた能勢町からの助言・勧告を踏まえた同計画や避難訓練等の内容を見直しが徹底されると認められるもの。
(2)土砂災害を防止し、又は軽減するための施設の整備等の防災対策が実施されているもの。
(3)上記と同等以上の安全性が確保されると認められるもの。
(浸水想定区域の場合)
(1)洪水等が発生した場合に、水防法第15条第1項に基づき能勢町地域防災計画に定められた同項第2号の避難場所への確実な避難にあたり、開発行為及び建築行為をしようとする者、建築物の所有者、占有者又は管理者等により作成された避難確保計画の能勢町長への報告、同計画に基づいた避難誘導等の訓練の実施、かつ訓練結果報告を受けた能勢町からの助言・勧告を踏まえた同計画や避難訓練等の内容を見直しが徹底されると認められるもの。
(2)上記と同等以上の安全性が確保されると認められるもの。
「都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」 第5における土砂災害警戒区域での開発行為等に関する取扱い (PDFファイル: 205.5KB)
災害に強いまちづくりをめざして ~ハザードマップを確認してください~
(平成30年9月1日施行)市街化調整区域の幹線道路沿道等における工場棟の立地を目的とした開発許可基準
この度、本町の市街化調整区域における開発行為等に関する大阪府開発審査会への新たな提案基準を設けました。これより、関連法令及び提案基準の要件を満たしている案件については、大阪府開発審査会の議を経て、許可を受けることにより、工場やその他産業施設の新たな建築等が可能となります。
(新たな基準制定の背景)
本町の市街化区域で工場等の立地が可能な準工業地域は、概ね土地利用がなされており、未利用地である土地も狭小であることから、新たな産業を誘致することは困難な状況にあります。今後、新たな産業を誘致することにより雇用の創出・人口減少(特に若者の流出)の抑制・地域経済の活性化を図っていくためには、市街化調整区域の土地を有効に活用していく必要があります。
市街化調整区域における産業誘致については、基本的に地区計画制度を活用することとしていますが、地区計画は5000平方メートル以上が要件であることから、この度、地区計画の対象とならない5000平方メートル未満の開発行為について許可基準を新たに制定しました。
(新たな基準の概要)
【許可対象行為】
工場等の新設、既存の建物の用途変更、既存の工場等の増築に伴う敷地拡大
【許可対象区域】
市街化区域に隣接する土地又は別図の5路線沿道の土地を対象としています。(別図参照)
【許可対象用途】
準工業地域で建築可能な用途を許可対象とするものであり、工業地域や工業専用地域でしか建築できない用途(危険性が大きいか又は環境を著しく悪化させるおそれがある工場)は許可対象としていません。
「許可できない用途の例(一部) 建築基準法別表第二(る)より」
・火薬類、ガス、化学物質、アスファルト、セメント、肥料等の製造
・製紙、製皮
・金属の溶接、精錬、鍛造
(注釈)
この提案基準による開発行為等は、市街化調整区域の何処であっても可能というものではありません。関係法令等及び提案基準の要件を満たす必要があります。また開発許可にあたっては地元地区等関係者との調整結果を踏まえて判断することとしております。市街化調整区域での土地利用や既存建築物の増築・用途変更をご検討される際は、先ずは下記お問い合わせ先へご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
まちづくり推進部都市整備課土木建築担当(西館2階)
電話:072-734-1726
ファックス:072-734-1545
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2025年07月01日